
※2024年1月から適用される電子取引データに関する電子帳簿保存法の改正内容に併せて大幅に記事の内容を修正いたしました。(2023年11月6日)
データで受け取った領収書が紙で保存できなくなるって知ってる?
電子帳簿保存法ってやつが改正されて、2024年1月からは事業を営んでいる人はみんな対象らしいよ。
あ、それ最近聞いた。よく知らないけど。
でも私は、請求書は紙で郵送してるし、私には関係ないと思うんだけど…
備品をAmazonで購入したりしてない?
あれも領収書をダウンロードするから、該当するらしいよ。
コピー用紙買ったり、書籍買ったりしてるわ。
Amazonも入るんだー
Amazonの領収書が紙での保存がダメならどうすればいいのかしら?
それは、タイムスタンプを押したり、金額なんかで検索できるようにしたりしなきゃいけなくて…
それで…削除できないシステムが…う…あ…
実は俺もわかんない。
電子帳簿保存法が改正されて、2024年1月から領収書等の電子取引データを電子的にやり取りした場合は、すべての事業者が、例外なく電子データのまま保存することが義務化されました。
2024年1月からは誰でも対応ができるような猶予措置も設けられましたので、「できるかなぁ?」といった心配はいりませんよ。
領収書等の電子取引データをやり取りした場合は、紙ではなくそのまま電子的に保存することが義務化されたということはだいぶ認知されてきているように思います。
事業を営んでいる法人や個人事業主がすべて対象ということで、世の中に与える影響は少なくないと言えます。
Amazonは、備品、事務用品や書籍の調達で多くの方が利用していますので、この電子帳簿保存法の改正でそれだけ多くの人が関わってくるものだと思い、Amazonの領収書を電子保存するところを切り口にこの制度がどういうもので、どのように対処すべきかまでわかりやすく解説していきます。
では、この記事の主題であるAmazonからダウンロードできる領収書は、そもそもこの電子帳簿保存法で義務化される電子保存の対象データなのかというところから始めていきましょう。
目次
1 Amazonの領収書は義務化された電子保存の対象か?

さて、Amazonの注文履歴から出力できる領収書は電子帳簿保存法で電子保存が義務化された対象なのでしょうか?

結論から言うと、「Yes!」です。
Amazonからダウンロードできる領収書は、義務化された電子取引データの電子保存の対象です。
この点を理解する上で、まず、この電子帳簿保存法による電子取引データの電子保存の義務化というものがどういうものかをざっくり確認しましょう。
電子取引データの電子保存の義務化とは?
① 事業を営んでいる個人事業主、法人は、例外なく
② 2024年1月から
③ 領収書や請求書等をメールやシステムで電子的に受領(交付)した場合は、
④ そのまま電子的に保存しなければならない。(紙で出力して保存は)
⑤ そして保存の仕方に一定の要件がある。(猶予措置あり)
概略はこのようになっています。
③の「領収書や請求書等をメールやシステムで電子的に受領(交付)した場合」の中にAmazonや楽天といったASPからモノを購入し、そのサイトから領収書等をダウンロードするケースが該当します。
したがってAmazonの領収書等の電子取引データは、④電子的に保存しなければならない対象となっています。
そしてそれは、⑤にあるととおり、電子帳簿保存法に規定された一定の要件の下で、電子保存する必要があります。
一定の要件ってなんだか厳しそうね
これまでの電子帳簿保存法では厳しかったのですが、2024年からは猶予措置が設けられ、ほぼ誰でもが対応できる緩やかなものになりました。
その辺りを踏まえて、わかりやすく解説します。
2 Amazonの領収書をどのように電子保存すればいいのか?

それでは、電子帳簿保存法にしたがってAmazonの領収書はどのように電子保存すれば良いのでしょうか?
それはその事業者の状況によって違ってきます。
それをどのように判断するかを図解のフローチャートの形でお見せします。

これから順を追って解説していきますが、質問に2択で回答していくことで、その人の置かれている状況に応じてどのように対応しなければならないかがわかるようになっています。
フローチャートの質問に答え始める前に、Amazonを利用している時点で、実は電子帳簿保存法における領収書等の電子取引データを電子保存するための3つの要件のうち2つが通常満たされているということを最初に確認しておきたいと思います。
電子帳簿保存法の特徴を掴む意図も含まれていますので、少し難しいですがついてきてください。
3 Amazonを利用している時点で電子帳簿保存法の要件を2つ満たしている

Amazonを利用している時点で、実は電子帳簿保存法で定められている領収書等の電子取引データを電子保存するための3つの要件のうち2つをすでに満たしているという意味を解説します。
電子取引データの電子保存の要件は、大きく以下のとおり3つあります。
- コンピュータ、ディスプレイとプリンタの備え付け
- 不正な改ざん防止策を講じる
- 検索機能の確保
この内容を1つ1つ簡単にチェックしていきますが、ここで1つ目の要件がクリアされることを説明します。
1-1 コンピュータ、ディスプレイとプリンタの備え付けはプリンタさえ対応できればOK
まず、1つ目の「コンピュータ、ディスプレイとプリンタの備え付け」は、税務調査のときに調査官が電子保存された電子取引データを実際に確認する必要があるので、これらの備え付けが求められています。
Amazonを注文している時点で、パソコンやスマホ、タブレット等なんらかのコンピュータを持っていることになります。
これで、コンピュータとディスプレイの要件は満たします。
プリンタについては、ない場合は、近隣に有料コピー機があって、速やかに印刷できれば問題ないことになっています。
これもできず、持っていない場合は、購入する必要があります。
このプリンタの問題を解決できれば、1つ目の要件は満たすことになります。
2つ目の「不正な改ざん防止策を講じる」については、PDFの領収書などの電子取引データは改ざんが容易で、しかも改ざんが行われたものかどうかの判断が難しいため、改ざんを防止する対策を講じることが求められています。
4つの方法のいずれかで、改ざん防止策をする必要があるのですが、結論から言うとAmazonを利用している時点でこの要件を満たしているので、Amazonの領収書データの電子保存を考えた時に特別意識する必要は通常ありません。
詳しくは次の章で解説します。
3つ目の「検索機能の確保」については、ある電子取引データを確認したいとなったときにそれを例えば取引先名や金額、日付で検索してすぐに見つけられるようにすることが求められます。
これは、税務調査の際に、確認が必要な請求書や領収書等の電子取引データを容易に検索でき、すぐに確認できるようにすることが目的です。
ここまでで、1つ目の「コンピュータ、ディスプレイとプリンタの備え付け」は、前述のようにプリンタだけ個々で対応する形で要件は満たすことになることを理解いただけたと思います。
次に、2つ目の「不正な改ざん防止策を講じる」については、どのような形で満たしているかを確認していきます。
1-2 Amazonを利用していることで「不正な改ざん防止策を講じる」要件を満たしている理由
電子取引データを電子保存するための2つ目の要件は、以下の4つの方法のいずれかで「不正な改ざん防止策を講じる」ことを求めています。
❶ データの訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないシステムを利用して電子取引データをやりとりする
❷訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
❸タイムスタンプが付与された後に電子取引データをやりとりする
❹7営業日以内に(又は最長2ヶ月+7営業日以内に※)タイムスタンプを付す
※ 括弧書の取扱いは、取引情報の授受からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。(超難関)
Amazonの領収書データは、基本的には、❶「データの訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないシステムを利用して電子取引データをやりとりする」方法で不正な改ざん防止策を講じることになります。
この「データの訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないシステムを利用して電子取引データをやりとりする」については、具体的には、2つの方法が存在します。
- Amazonのシステム自体がこれに該当するので何もする必要がない
- クラウド会計とAmazonアカウントを連携する方法
それぞれについて詳しく確認していきましょう。
1-2-1 Amazonのシステム自体が訂正削除できないシステムなので何もする必要がない
まず1つ目の「Amazonのシステム自体がこれに該当するので何もする必要がない」について解説します。
Amazonの領収書は購買記録であるため、ユーザーがAmazonの「注文履歴」に表示されている内容を削除したり、訂正したりできません。
したがって、訂正削除ができないシステムであるAmazon内で領収書等の電子取引データがやりとりされているので、Amazonを使っているだけで電子帳簿保存法の「不正な改ざん防止策を講じる」という要件を満たします。
Amazonサイトにデータが保存されているだけで要件を満たすので、何もする必要がないのです。
1-2-2 クラウド会計とAmazonアカウントを連携する方法で要件を満たす
2つ目の「クラウド会計とAmazonアカウントを連携する方法」については、クラウド会計ソフトなどに代表される銀行口座やクレジットカードの明細等のデータを取り込むことができるサービスがありますが、そのシステムが「訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないシステム」になっていれば、これもこの方法の代表例となります。
したがってAmazonの取引を、訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないシステムであるクラウド会計ソフトに連携でき、取引明細をその会計ソフトに保存できれば、このクラウド会計ソフトのシステム内で要件を満たすことになります。
この方法であればクラウド会計で取引を取り込んで帳簿付けをしている日々の作業をしていれば、それで電子帳簿保存法の改ざん防止策を講じる要件を満たすので、こちらも手間いらずと言えます。
こちらの方法が優れているのが、クラウド会計で要件を満たしていればOKなので、他のオンラインサービスで電子取引データをやりとりしている場合に、以下のメリットがあります。
・そのサービスが電子帳簿保存法の要件に合致しているかをいちいち確認する必要がない。
・電子取引データを一元管理できる
ちなみにAmazonは電子帳簿保存法の3つ目の要件である「検索機能の確保」を満たしていません。クラウド会計ソフトで電子帳簿保存法対応の場合は通常満たしています。(満たしていなくても猶予措置でクリアできるので、そういう方には関係ありませんが。後述)
また、電子取引データの確認が必要になったときに、色々なオンラインサービスがあった場合、その都度そのサービスでどこに保存しているかを探すのも面倒ですよね。
したがって、いつも使っているクラウド会計に集約されていると整然としていて便利なのです。
ただしこのクラウド会計を使う方法は、消費税を申告する義務があり、かつ原則課税の方法で申告する場合は、インボイスの保存要件を満たしませんので、この方法だけでは、消費税の仕入税額控除の要件を満たさなくなることに注意が必要です。詳しくは後述します。
ここまでで、Amazonのシステムを使っている時点で「不正な改ざん防止策を講じる」という電子帳簿保存法の2つ目の要件を満たしているということを確認してきました。
具体的に4つの方法があってそれぞれAmazonに直結する解説しかしていませんので、その他の方法も含め、「不正な改ざん防止策を講じる」要件の包括的な理解を進めたい方は、次の記事で詳しく解説していますので、こちらをご参照ください。
なお、3つ目の「タイムスタンプが付与された後に電子取引データをやりとりする」という要件については、Amazonからダウンロードできる領収書には公式から以下の記載があり、タイムスタンプがついていませんので、この要件はAmazonのシステムだけでは満たしません。
尚、Amazonが発行する請求書等の電子データについて、タイムスタンプの付与はありません。
ここまでで、Amazonを利用している時点で、電子帳簿保存法で求められている3つの要件のうち2つを満たしていることを確認できました。
ここからは、冒頭で紹介したフローチャートの詳細を確認し、ご自身がAmazonを利用した場合にどのような対応をする必要があるのかを確認していきましょう。
それでは最初の質問に入っていきましょう。
Q1 電子帳簿保存法の「検索機能の確保」要件を満たしているか?

前述の電子取引データに関する電子帳簿保存法の3要件のうちの3番目の「検索機能の確保」に関する質問です。
Amazonのシステムでは、この「検索機能の確保」要件を満たしませんので、別途自社で用意する必要があります。
そこで1つ目の質問です。
・取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索できる
・日付又は金額について、その範囲を指定して検索できる
・2以上の任意の項目を組み合わせて検索できる
これだけの文章を読んで、これを理解していて、実際に実行もできる人は、「YES」と回答してください。
ちょっと意味がわからないという人は、「NO」と回答してください。
Q1の回答:YESの場合(検索機能の確保ができている)
あなたは、すでに電子帳簿保存法のことをよく理解され、すでに対応済みですね。
Amazonには、電子帳簿保存法の要件を満たす検索機能はありませんので、おそらく次の方法で検索機能を確保していると推測されます。
- クラウド会計ソフトとAmazonアカウントを連携し、ソフトの検索機能を利用する
- 電子取引データ等の一元管理ソフトの検索機能を利用する
- 表計算ソフトのフィルタ機能等で検索する
Q1の問いにYESの方は、ここでフローチャート完了です。
Amazonの領収書データを電子帳簿保存法のルールに則して電子保存できています。
クラウド会計で検索機能を確保している場合で、消費税を申告する義務がある方は、次の点だけ注意してください。
原則課税の方法で申告する場合は、インボイスの保存要件を満たしませんので、この方法だけでは、消費税の仕入税額控除の要件を満たしません。
別途インボイス対応が必要です!(インボイス対応はこちらをクリック)
Q1の回答:NOの場合(検索機能の確保ができていない)
Q1の検索機能の確保について、よくわからなかった方やそういった機能を持っていない方は、次の質問に答えてください。
検索機能の確保自体どういうものか知りたいという方は、次の記事で詳しく解説しています。
この記事を読んで理解したとしても現時点でその対応ができないという場合もQ1の回答は「NO」になります。
Q2 基準期間の売上高が5,000万円以下か?

基準期間とは、原則的には次の期間を指します。
| 個人事業主 | 法人 |
|---|---|
| 電子取引が行われた日の属する年の前々年 | 電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度 |
またここでいう売上高とは、損益計算書で「売上高」と経理する本業によって得た収益を意味し、雑収入等の営業外収入や特別利益を指しません。
| 個人事業者の売上高 | 法人の売上高 |
|---|---|
| 「商品製品等の売上高、役務提供に係る売上高、農産物の売上高(年末において有する農産物の収穫した時の価額を含みます。)、賃貸料又は山林の伐採又は 譲渡による売上高」をいい、家事消費高及びその他の収入は含まれません。 | 「一般的に売上高、売上収入、営業収入等として計上される営業活動から生ずる収益」をいい、いわゆる営業外収益や特別利益は含まれません。 |
「基準期間の売上高」と消費税の「基準期間の課税売上高」とは意味が異なります。
「基準期間の売上高」については、次の記事で詳しく解説しています。
Q2の基準期間の売上高が5,000万円以下の場合は、YESの方へ、5,000万円を超える場合は、NOの方へ進んでください。
Q2の回答:YESの場合(5,000万円以下)
基準期間の売上高が5,000万円以下の場合は、次の対応ができていれば、「検索機能の確保」要件が免除されます。
- Amazonの領収書等データ
- Amazonの領収書等データを紙に印刷したもの※
※求めに応じてなので、予め印刷しておく必要はありません。
上記のことをできるようにしておけば、検索機能の確保要件は不要となり、Amazonの領収書データを電子帳簿保存法のルールに則して電子保存できていることになります。
フローチャートはここで完了です。
Q2の回答:NOの場合(5,000万円超)
Q2の問いにNO、つまり基準期間の売上高が5,000万円超の場合は、次の質問に答えてください。
Q3 ソフト等を使って検索機能の確保要件を満たす体制がとれるか?

・クラウド会計ソフトにAmazonアカウントを連携する
・電子取引データを一元管理できる電子帳簿保存法対応ソフトを使う
・AmazonビジネスでCSV出力し、表計算ソフトの検索機能を使う
これらの3つの方法が「検索機能の確保」要件を満たすためにとりうる主な方法です。
これからそれぞれの方法を解説しますが、これらの方法をとれる場合は、回答は「YES」です。「うちの会社では無理だ」という場合は、回答は「NO」です。
検索機能の確保要件を満たすためにとりうる3つの方法
① クラウド会計ソフトにAmazonアカウントを連携する方法
クラウド会計で「検索機能の確保」要件を満たそうとするわけですが、その前にお使いのクラウド会計ソフトが電子取引データの電子帳簿保存法に対応しているかを確認する必要があります。
具体的には次の2点を確認してください。
不正な改ざん防止策が講じられているシステムか
電子帳簿保存の2つ目の要件の「不正な改ざん防止策を講じる」方法の4つのうちの1つ「データの訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないシステムを利用して電子取引データをやりとりする」という要件にクラウド会計ソフトが該当している必要があります。
つまり、お使いのクラウド会計ソフトに取り込んだAmazonの取引データが削除訂正ができないシステムであることが前提です。
通常はクラウド会計ソフトは取り込んだ取引明細を個々に削除訂正することはできません。
これは最初に確認するようにしてください。
連携を解除することで全データを削除することはできますが、それは絶対にしないというのも前提です。
「検索機能の確保」要件を満たす検索機能があるか
次の3つの検索機能があるかも確認してください。
・取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索できる
・日付又は金額について、その範囲を指定して検索できる
・2以上の任意の項目を組み合わせて検索できる
以下の画像は、あるクラウド会計ソフトのAmazonビジネスの取引データを取得した一覧画面です。
上記3つの検索ができるようになっていることを確認できるかと思います。

上記2つの要件を満たしていれば、電子取引に関する電子帳簿保存法の要件を満たしています。
クラウド会計ソフトだけで、電子帳簿保存法の要件を満たしていますので、Amazonのアカウントを削除したとしても大丈夫です。
ただし、原則課税で消費税を申告する場合は、インボイス(適格請求書)を保存する必要があるので、クラウド会計ソフトだけでは消費税法の仕入税額控除の要件を満たさなくなるので、ここは注意です。(後述)
② 電子取引データを一元管理できる電子帳簿保存法対応ソフトを使う方法
一元管理できるソフトと言われてもよくわからないという場合もあるかと思いますので、具体的に当社が運用している「全力電子帳簿」というソフトを例にどのように「検索機能の確保」要件を満たすかを見ていくことにします。
❶ 領収書等の電子データを保存する
次のAmazonの領収書を「全力電子帳簿」に保存してみます。
【STEP1】 電子取引データ保存画面にPDFファイルをアップロードする
アップロードが完了したら
【STEP2】電子取引データの内容をフォームに入力する
入力が済んだら保存する。
一覧画面で登録した電子データの内容を確認できます。
「検索機能の確保」要件に合った検索がもちろん可能です。
取引先名で検索してみます。
このように「取引先」に記載した文字で検索することができます。
ここで、全力電子帳簿の宣伝をさせてもらうと、全力電子帳簿は格安で電子取引データを一元管理できるソフトです。操作もとてもシンプルでわかりやすくく、ワンコインから始められます。
全力電子帳簿の料金システム
| 月10枚まで | 月100枚まで | 月200枚まで |
|---|---|---|
| 月額100円 | 月額500円 | 月額1,000円 |
電子取引データ10枚までの電子保存は無料でお試しできます。
※金額は税抜
全力電子帳簿のような電子取引データを一元管理できるソフトを使用するとAmazonだけでなく、他の電子取引データを一括で管理できるというメリットがあります。
Amazonの領収書以外にも必ず電子取引データのやり取りを行うことになるかと思いますので、このようなソフトを使ってスマートに対応するという方法も、この面倒な電子保存に対応する賢い選択かと思います。
クラウド会計ソフトは連携すればそれでOKなので、手間の面ではクラウド会計ソフトの方が楽でしょう。
③ AmazonビジネスでCSV出力し、表計算ソフトの検索機能を使う
これまで紹介したクラウド会計ソフトも一元管理ソフトも基本的には使用料金がかかってきます。
コストをかけずに対応する場合は、表計算ソフトの検索機能を使う方法があります。
この方法は、Amazon Businessで注文履歴をCSV形式で出力し、それをエクセル等の表計算ソフトのフィルタ機能を使って検索機能の確保を行うというものです。
なぜ、Amazon Businessなのかというと、注文履歴をCSV形式で出力できるのがAmazon Businessだけだからです。
そうでない通常のAmazonでは、サイトから公式に注文履歴をCSV形式で出力する方法はありません。(非公式の拡張機能等を駆使してする方法もあったりしますが、正確性は担保されません。)
Amazon Businessは、法人と個人事業主が無料で始められるので、電子帳簿保存法に効率的に対応するためにAmazonで注文しているものをAmazon Businessに切り替えるのが得策だと思われます。
なぜなら、Amazonの注文履歴をエクセルにベタうちしたいと思いますか?
手間いらずでCSVにしてもらってそれを検索する方が圧倒的に楽ですよね?
それでは、Amazon businessを使ってどのように検索機能を確保していくかを解説していきます。
Amazon businessは、ビジネス用のAmazonサービスです。
(参考)Amazon Businessがよくわからないという方は公式が次の記事を出しています。
Amazonビジネスでの購買は、個人向けのAmazon.co.jpと何が違うのか?
Amazon BusinessでどのようにCSV出力するかを見ていきましょう。
【手順1】Amazon Businessにログインします。
【手順2】メニューからアカウントサービスをクリックします。

【手順3】購買データを選択する。

【手順4】注文履歴データを選択する。

【手順5】CSVデータをダウンロードする。

【手順6】CSVデータを加工する。
税務で必要となる列だけ残してそれ以外は削除すると見やすくなるでしょう。
必須の列:「日付」、「注文番号」、「経理した金額と一致する金額が載っている列」、「出品者名」

< CSV方式での検索方法 >
検索の際は、表計算ソフトのフィルタ機能を使って検索します。
ここではエクセルを使った例を紹介します。

(商品の金額で検索した例)
検索してヒットした行の「注文番号」をコピーし、注文履歴画面の検索窓にペーストして「注文を検索」ボタンを押して検索。
ヒットした注文履歴の「領収書等」から領収書等を出力する。

このようにAmazon Businessでcsv出力すれば難なく検索が可能です。
表計算ソフトの検索機能を使って、電子帳簿保存法の以下の3つの検索機能の確保要件を満たすかの詳細を解説していきます。
- 取引年月日、取引金額及び取引先を検索できる
- 日付又は金額については、その範囲を指定して検索できる
- 2以上の任意の項目を組み合わせて検索できる
表計算ソフトのフィルター機能を用いる方法には次の2つの方法があります。
- 国税庁が公表している索引簿を作成する方法(索引簿方式)
- 何らかの方法でAmazonの購入履歴をcsv形式で出力する方法(csv出力方式)
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 索引簿方式 | 国税庁が示す索引簿を作成できる | 取引の都度必要なデータを入力するのが手間 |
| csv出力方式 | 必要なデータがすでにファイルに入力されているので楽 | 自身の環境により使えるcsvデータが手に入らない可能性がある |
まずは、国税庁が公表している電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】の問12、問33で解説している方法(索引簿方式)を紹介します。
索引簿方式
表計算ソフトで次のような索引簿を作成して、表計算ソフトのフィルタ機能で検索する方法です。

この索引簿のサンプルは国税庁の「参考資料(各種規程等のサンプル)」ページの「索引簿の作成例」からダウンロードできます。
索引簿をどのように作成していくかをAmazonに当てはめて解説します。
< 索引簿作成方法 >
この方法にもAmazonの領収書を処理するにあたって2通りのやり方があります。
- 領収書データをダウンロードして、フォルダを1つ用意してそこにすべて保存する方法
- 領収書データは必要な都度Amazonサイトからダウンロードする方法。
1つ目を採用する理由としては、先ほど挙げたように、個人的な購入がある場合に、第三者に見られたくない場合や、保存期間が心配な場合です。
1つ目の領収書データをダウンロードして、フォルダを1つ用意してそこにすべて保存する方法から解説していきます。
この方法は、Amazonに限らず、メールで領収書を受領した場合等、電子取引データをやり取りした場合には、すべて使える方法なので、この方法は覚えておく必要があります。
ケース1 データをフォルダに保存するやり方
【手順1】
電子取引データを保存するフォルダを作成します。

【手順2】
Amazonサイトから領収書をダウンロードし、ファイル名を1から順に連番を振っていきます。
ファイル名を変更したら、【手順1】で作成したフォルダに保存します。

※ファイル名は単純に「1」とすると検索の際に見つけづらいので、「001」としています。
ファイル名を複雑にすればするほど見つけやすくなりますが、それに反比例して入力が面倒になりますので、見つけやすいくらいの独自性がありつつ簡単めなファイル名にしましょう。
【手順3】
ファイル名(番号)と一致する索引簿の「連番」の行に対象の電子取引データから必要なデータを転記します。
今回の例では、ファイル名を「001」にしていますので、索引簿の「連番」の①の行に対象の請求書データに記載されている「日付」「金額」「取引先」を入力します。

なお、取引先は、すべてアマゾンジャパン合同会社からとは限りません。
Amazonへの出店者の可能性もありますので、領収書に記載された取引先名を入力しましょう。
次の電子取引データは、ファイル名を「002」にして【手順1】で作成したフォルダに保存し、索引簿の「連番」②の行に必要な情報を入力する。
これをこの後の電子取引データに対しても繰り返していきます。
次にこのようにして作成した索引簿でどのように必要な電子取引データを検索するかを解説します。
< 索引簿検索方法 >
電子帳簿保存法の検索要件は次の3つでした。
- 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索できる
- 日付又は金額については、その範囲を指定して検索できる
- 2以上の任意の項目を組み合わせて検索できる
エクセルを例に、この要件をどう満たしていくかを解説します。
まず次のように、タイトルを選択し、フィルタをクリックして、フィルタ機能を追加します。
これにより色々な種類の検索が可能になります。

⑴ 一つ目の検索要件「取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索できる」については、次のように満たすことができます。
① 日付の検索
【手順1】エクセルファイルの「日付」タイトルのセルにある「▼」をクリックすると「日付」というフォームが出てくる。
【手順2】フォームの検索窓に検索したい日付を入力する。

検索の例は、Amazonのものではなく、簡略化したもので説明します。
この例では「20220228」(2022年2月28日)を検索し、6行目がヒットしています。
② 金額の検索
【手順1】エクセルファイルの「金額」タイトルのセルにある「▼」をクリックすると「金額」というフォームが出てくる。
【手順2】フォームの検索窓に検索したい金額を入力する。

今回の例では、「55000」を検索し、7行目がヒットしています。
③ 取引先の検索
【手順1】エクセルファイルの「取引先」タイトルのセルにある「▼」をクリックすると「取引先」というフォームが出てくる。
【手順2】フォームの検索窓に検索したい取引先を入力する。

今回の例では、「いろはに電気」を検索し、8行目がヒットしています。
これで1つ目の要件はクリアです。
⑵ 続いて2つ目の要件「日付又は金額については、その範囲を指定して検索できる」をどのように満たすか見ていきましょう。
① 日付の範囲指定の方法
日付の範囲指定から説明します。
【手順1】エクセルファイルの「日付」タイトルのセルにある「▼」をクリックすると「日付」というフォームが出てくる。
【手順2】「フィルター」の選択肢から、「指定の値以上」を選択し、範囲の開始の日付を入力する。

今回の例では、2022年2月1日からの範囲指定で、「20220201」と入力しています。
【手順3】指定の値以下を入力する。
手順2の入力が終わるともう一つ選択肢が表示されるので、「および」を選択し、さらに選択肢から「指定の値以下」を選択し、範囲の終わりの日付を入力します。

今回の例では、2022年2月28日までを検索したいので、「20220228」を入力しています。
このように20220201〜20220228(2022年2月1〜2022年2月28日)の範囲のデータのみが表示されます。

② 金額の範囲指定の方法
①と同様のやり方で金額の範囲指定を行なっていきます。
400,000〜600,000で範囲指定をする例で説明します。
エクセルファイルの「金額」タイトルのセルにある「▼」をクリックするとフォームが出てきます。
「フィルター」の選択肢から、「指定の値以上」を選択し、「150000」と入力し、「および」と「指定の値以下」を選択し、「300000」を入力し、「enter」を押すと、その範囲の金額の行のみが表示されます。

⑶ 次は3つ目の要件「2以上の任意の項目を組み合わせて検索できる」を満たす方法です。
例として、日付「2022年2月10日」と取引先「アマゾンジャパン」を同時に満たすの領収書を検索してみます。
【手順1】
取引先のフィルターの検索窓に「アマゾンジャパン」と入力し、「enter」を押します。

【手順2】
日付のフィルターの検索窓に「20220210」と入力し、「enter」を押します。

すると↑の画像のようにこの2つの検索条件に合致する行のみが表示されることがわかります。
フィルターの検索機能で、3つの検索要件をすべて満たすことが確認できました。
Amazon Businsessのcsv出力機能を使えば、このような表計算ソフトのフィルター機能を使うことにより検索要件を満たすことができます。
ここまで3つの方法で「検索機能の確保」要件を満たす方法を紹介してきました。
・クラウド会計ソフトにAmazonアカウントを連携する
・電子取引データを一元管理できる電子帳簿保存法対応ソフトを使う
・AmazonビジネスでCSV出力し、表計算ソフトの検索機能を使う
ここで再度質問です。
これらの方法をとれる場合は、回答は「YES」です。「うちの会社では無理だ」という場合は、回答は「NO」です。
「これらの方法がとれるか?」「うちの会社では無理だ」と言われてもどの程度のニュアンスかわからないかと思いますので、説明を加えます。
国税庁は、上記の方法で「検索機能の確保」要件を満たすのに「システム等や社内でのワークフローの整備が間に合わない場合等」という表現を使っています。
これを参考に別の問いかけをしてみます。
上記3つの方法で「検索機能の確保」要件を満たすためのシステム等や社内でのワークフローの整備が間に合うか?
間にある場合は、回答は「YES」です。間に合わない場合は、回答は「NO」です。
Q3の回答:NOの場合(ソフト等の導入無理・間に合わない)
次の対応ができていれば、電子帳簿保存法のルールに則して電子保存できていることになります。
- Amazonの領収書等データ
- Amazonの領収書等データを紙に印刷したもの※
※求めに応じてなので、予め印刷しておく必要はありません。
電子帳簿保存法の保存要件について、対応するための準備が間に合わないという理由で上記の対応をすれば、保存要件のすべてが免除される猶予措置が適用されます。
したがって、クラウド会計ソフト等を導入して対応することができない場合は、猶予措置が適用され、Amazonの注文履歴に取引データがあれば、OKということになります。
電子取引データに関する電子帳簿保存法の猶予措置とは
猶予措置とは、次の2つの条件を満たすときには、前述の電子帳簿保存法の3つの保存要件を満たしていなくても電子保存を認めるというものです。
❷ 電子取引データと電子取引データを出力した書面を税務職員からの要求に応じて提示もしくは提出できるようにしている場合
「所轄の税務署長が電子取引データの保存を要件どおりにできなかったことについて、相当の理由があると認める」ケースは「例えば、システム等や社内でのワークフローの整備が間に合わない場合等」は相当の理由になると国税庁が公表しています。
こういった理由があれば、検索機能の確保を含む3つの保存要件を満たさなくてよいというのが猶予措置です。
この場合でも、領収書等のデータを電子保存しなければならないのは、変わりません。紙に印刷して保存することはこの猶予措置でも認めていないことに注意しましょう。
税務職員に取引データを求めに応じて提出できるようにしていれば、電子帳簿保存法の3つの保存要件がすべて免除され、Amazonの領収書データを電子帳簿保存法のルールに則して電子保存できていることになります。
フローチャートはここで完了です。
Q3の回答:YESの場合(ソフト等の導入OK・間に合う)
すでに解説した以下の3つの方法等を駆使して検索機能の確保の要件を満たせる体制をとれる場合は、ここで電子帳簿保存法の要件をすべて満たします。
・クラウド会計ソフトにAmazonアカウントを連携する
・電子取引データを一元管理できる電子帳簿保存法対応ソフトを使う
・AmazonビジネスでCSV出力し、表計算ソフトの検索機能を使う
電子帳簿保存法の話だけであれば、ここですべて完了なのですが、最後に消費税のインボイス(適格請求書)について確認が必要ですので、最後の質問に答えてください。
Q4 消費税の申告義務があり、かつ簡易課税や2割特例で申告するか?

消費税のインボイス(適格請求書)の対応が必要かを確認する質問です。
YESの場合は、インボイスの保存義務がなく、NOの場合は、インボイスの保存義務があり、それにより対応方法が違ってきます。
Q4の回答:YESの場合(消費税申告義務なし又は簡易課税か2割特例で申告する)
消費税の申告義務がないか、または、申告義務があったとしても、簡易課税または2割特例を適用して申告する場合は、以下の方法等を導入して「検索機能の確保」要件を満たせば、電子取引データに関する電子帳簿保存法のルールに則って電子保存できていることになります。
消費税の申告義務がないか、または、申告義務があったとしても、簡易課税または2割特例を適用して申告する場合は、すでにAmazonの領収書データを電子帳簿保存法のルールに則して電子保存できていて、消費税のインボイス対応も不要であることが確認できたので、フローチャートはここで完了です。
Q4の回答:NOの場合(消費税を原則課税で申告する)
消費税の申告義務があって、原則課税で申告する場合は、仕入税額控除するためには、インボイス(適格請求書)の保存が必要になります。
ここで注意すべきは、次の事項です。
クラウド会計ソフトで電子保存した場合の注意点
なぜならインボイス制度では、仕入税額控除する要件として、次の事項が確認できるインボイス(適格請求書)を保存する必要があるからです。
| 記載の必要な項目 | |
|---|---|
| ❶ | インボイス発行事業者の名称と登録番号 |
| ❷ | 取引年月日 |
| ❸ | 取引内容(軽減税率の対象である旨も) |
| ❹ | 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率 |
| ❺ | 税率ごとに区分した消費税額等 |
| ❻ | 書類の交付を受ける事業者の名称 ※不特定多数の場合は不要 |
クラウド会計ソフトでAmazonアカウントを連携して取得できる情報は、これらすべての情報を取得できません。
したがって、クラウド会計ソフトで連携しているだけでは、電子帳簿保存法ではOKだが、消費税の仕入税額控除の要件を満たさないという片手落ちの状態になります。
それではどうしたらよいかというと、次の方法等を使って、次のようなインボイス(適格請求書)を保存して、それ自体を取引データとして持っている必要があります。

消費税の仕入税額控除の要件には、電子データで保存することは義務になっていませんので、紙に印刷することも認められます。
対応方法としては、以下の4つの方法が考えられます。
❶ クラウド会計ソフトは検索機能としてだけ使い、実際のAmazonの領収書等のデータは、Amazonのシステムからダウンロードする方法
❷ Amazonの領収書等のデータをダウンロードして、一元管理ソフトにアップロードする方法
❸ Amazonの領収書等のデータをダウンロードして、実際のAmazonの領収書等のデータは、Amazonのシステムからダウンロードする方法
❹ Amazonの領収書等のデータをダウンロードして印刷して紙で保存する方法
せっかく電子保存しているのに紙に印刷するのは避けたいですね。
ここまでの方法で、Amazonの注文履歴で管理されている領収書等のデータをその事業者の状況に応じてどのように電子保存すればよいかを、Q&A方式で解説してきました。
保存の方法はここまででわかりましたが、最後に電子保存したデータを何年間保存する必要があるのかという点に触れたいと思います。
4 オンラインサービスを使用してやりとりした領収書等のデータを電子保存する際の留意点

ここまで、Amazonの領収書等データを電子帳簿保存法にルールどおりに電子保存する方法について、解説してきました。
ここからは、Amazonを含め、クラウドサービスで領収書等をやりとりした場合全般の留意点を確認していきたいと思います。
帳簿書類の保存期間は次のように所得税法と法人税法で決められています。
帳簿書類の保存期間:個人事業主では最長7年、法人では最長10年
詳しくは次の記事で解説しています。
Amazonは訂正削除できないシステムだから、「不正な改ざん防止策を講じる」という要件を満たしているという説明をしました。
ECサイトや他のクラウドサービスでも領収書をやりとりした場合にそれは商取引の証拠になるものですので、通常は削除できないはずです。したがってAmazon以外のオンラインサービスでも通常は「不正な改ざん防止策を講じる」という要件を満たすはずです。
しかしながら、その取引履歴等のデータが未来永劫保存されるかはそのサービス次第だと思われます。
したがって、領収書等のデータをオンラインサービス上に保存する場合は、必ずそのデータが何年保存されるものかを確認しましょう。
4-1 保存期間を確保するためにAmazonビジネスを使う
この保存期間の問題を確実にクリアするためには、Amazonの場合は、必ずAmazonビジネスを使うようにしましょう。
それは、AmazonビジネスではないAmazonサイトの注文履歴が何年間保持されるかが実は公言されていないことです。
Amazonの注文履歴が消えないのではないかというのが多くの意見のようですが、確証はありません。
Amazon Businessでは10年と言っていますが、通常のAmazonはわからない状況です。

執筆時現在Amazonビジネスでないアカウントの注文履歴は10年以上保存されていることは確認されてはいます。
ただし、Amazonサイトで注文履歴が帳簿の保存期間に渡って保存される確証がないので、保存期間前に注文履歴が削除され、その間の証拠書類が失われるというリスクがあることを理解しておく必要があります。
それが不安な場合は、Amazon Businessを利用することで対応を図りましょう。
5 まとめ

Amazonの注文履歴から出力される領収書等のデータをどのように電子帳簿保存法のルールにしたがって保存すればよいかを解説してきました。
この方法は、Amazonに限った対応方法ではなく、他のオンラインサービス上で領収書等をやりとりした場合にも広く当てはまります。
ここで再度、Amazonを中心としたオンラインサービス上で領収書等をやりとりした場合に自分はどのように保存すればよいのかを確認できるようにフローチャートを貼っておきます。

電子取引データに関する電子帳簿保存法で、ポイントとなる点を確認しましょう。









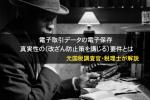










コメント