
電子帳簿保存法が2023年(令和5年)に改正になり、電子取引データの電子保存が2024年(令和6年)1月から全事業者に例外なく義務化されます。
つまり、紙に印刷して保存することが今度こそ認められなくなりました。
当初は2022年1月から電子保存の義務化のはずが、二転三転し、その後2年経ったことにより、
結局私は何をすればいいの?
という状態になっている方が多いかと思います。
税理士の私でもそうでした。
そこで、請求書や領収書等の保存義務のある証ひょう類をメールやクラウド等のオンラインでデータで受け取ったり交付したりした際に、その事業者によってどのように電子保存をしなければならないかを、簡単な質問にYes or Noで答えることでわかるようにしたいと思います。
えー
どんなことしなければいけないんだろー?
たいへんだったら嫌だなー
安心してください。
電子取引データの電子保存について、現時点でよくわらないという方は、多くの場合で厳しい保存要件がすべて免除される猶予措置が適用されると思われます。
これが適用されると、電子データを単に電子保存しておいて、税務職員から提出を求められたら、そのデータと書面に出力して提出できればOKという逃げ場が用意されています。
詳しくは、質問に答えて確認してください。
これから行うQ&Aをペライチにすると次のようになります。

それでは、早速質問に答えて、自身がすべきことを理解してしまいましょう。
その前に、この記事の前提知識として、電子帳簿保存法の電子保存が義務化されたのは、領収書等をデータでやりとりした場合だけです。電子帳簿保存法は他にもスキャナ保存や会計帳簿等に関するものがありますが、これらの電子保存は任意で、紙での保存も認められています。
電子保存が義務化された対象が何なのかもわからない場合は、まずは次の記事の「2024年1月開始の電子帳簿保存法の概要」部分のみを参照して、どのような保存書類が電子保存が義務化されたかを確認してから戻ってきてください。
それでは、最初の問いからスタートです!
目次
【Q1】電子取引データを改ざん防止策を講じて保存する体制が整っているか?

最初の問いは、
※「電子取引データを改ざん防止策を講じて保存する」については、次の記事をご覧ください。
電子取引データを改ざん防止策を講じて保存する体制が整っているか?とは、上記の解説記事に以下の4つの方法のいずれかの方法で電子取引データを保存しなければならないという解説がありますが、それができるかどうか?という意味です。
- タイムスタンプが付与された後の授受
- 7営業日以内に(又は最長2ヶ月+7営業日以内に)タイムスタンプを付与する
※ 括弧書の取扱いは、取引情報の授受からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。(超難関) - 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
- データの訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないクラウドサービス等を利用して取引データをやりとりする
「できない」ということを、どの程度で言っていいかというと、これらの4つの方法に対応するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない場合に、「できない」と言ってよいことが国税庁のQ&Aで公表されています。
令和5年度の税制改正において創設された新たな猶予措置の「相当の理由」とは、例えば、その電磁的記録そのものの保存は可能であるものの、保存時に満たすべき要件に従って保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった、- 略 – 要件に従って電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情がある場合については、この猶予措置における「相当の理由」があると認められ、保存時に満たすべき要件に従って保存できる環境が整うまでは、そうした保存時に満たすべき要件が不要となります。
上記4つの方法のいずれか一つも、システムを導入して対応することも、事務処理規程を設けてその規程どおりに社内で運用することもできない場合は、この第1の問いに「No」と答えてください。(Noの場合に飛ぶ)
この4つの改ざん防止策のいずれか1つでも対応できる場合は、「Yes」と回答してください。(Yesの場合に飛ぶ)
【Q1】の回答が「No」の場合
【Q1】の回答が「No」の場合は、次の猶予措置の適用を受けることができます。
電子取引データの電子帳簿保存の猶予措置
次の要件をクリアしていれば、単に電子取引データを電子的に保存していればOK。
- その電子データ
- その電子データが書面で作成された場合に準じた形式で出力した書面
この2点を税務職員に提示又は提出することができるようにしている場合は、電子取引データの電子帳簿保存法で設けられている以下の3要件のすべてが免除されます。
- コンピュータ、ディスプレイとプリンタの備え付け
- 不正な改ざん防止策を講じる
- 検索機能の確保
電子取引データの電子保存の要件を満たすことができない場合は、その理由を説明して、この2点を税務職員に提示又は提出することができるようにしておけば、電子取引データの電子帳簿保存法に関しては、クリアということですね。
そうなります。
国税庁の電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問62では、この免除規定の適用に関して次のような解説があります。
「保存時に満たすべき要件に従って保存をすることができなかったことに関する相当の理由を確認させていただく場合もありますが、仮に税務調査等の際に、税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを具体的にご説明いただければ差し支えありません。」
と、かなり柔軟に対応する姿勢が垣間見えます。
このすべての電子保存の要件が免除される場合でも、電子的に保存する必要はあるので、紙に出力するのは認められていないことに注意しましょう。
猶予規定の適用を受ければ、電子帳簿保存法のルールに則った電子保存であることになりますので、ここで判断は終了です。
電子取引データに関する電子帳簿保存法の猶予措置について詳しく知りたい場合は、次の記事をご参照ください。
【Q1】の回答が「Yes」の場合
【Q1】の回答が「Yes」であった場合は、前述の4つの改ざん防止策のいずれかの方法を講じなければならないことは確定です。
これは絶対にやらなければなりません。
その上で【Q2】に進みます。
【Q2】基準期間の売上高が5,000万円以下か?

第2の問いは、
基準期間とは、次の期間を指します。
| 個人事業主 | 法人 |
|---|---|
| 電子取引が行われた日の属する年の前々年 | 電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度 |
またここでいう売上高とは、損益計算書で「売上高」と経理する、本業によって得た収益を意味し、雑収入等の営業外収入や特別利益を指しません。
| 個人事業者の売上高 | 法人の売上高 |
|---|---|
| 「商品製品等の売上高、役務提供に係る売上高、農産物の売上高(年末において有する農産物の収穫した時の価額を含みます。)、賃貸料又は山林の伐採又は 譲渡による売上高」をいい、家事消費高及びその他の収入は含まれません。 | 「一般的に売上高、売上収入、営業収入等として計上される営業活動から生ず る収益」をいい、いわゆる営業外収益や特別利益は含まれません。 |
基準期間の売上高」については、次の記事で詳しく解説しています。
【Q2】の回答が「Yes」の場合
【Q2】の回答が「Yes」であった場合は、
つまり、【Q2】の回答が「Yes」の方は、前述の改ざん防止策を講じていれば、それで電子取引データに関しては、電子帳簿保存法で認められた電子保存が行われていることになります。ここで判断は完了です
【Q2】の回答が「No」の場合
【Q2】の回答がが「No」であった場合は、第3の問いに進んでください。
【Q3】電子取引データを出力した書面を取引年月日等及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしているか?

第3の問いは、
取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理とは、具体的には、次のいずれかの方法で整理することが求められています。
❶ 決算期(または年分)ごとに、取引年月日その他の日付の順にまとめた上で、取引先ごとに整理する方法
❷ 決算期(または年分)ごとに、取引先ごとにまとめた上で、取引年月日その他の日付の順に整理する方法
❸ 書類の種類ごとに❶または❷と同様の方法で整理する方法
この3つの方法のいずれかの方法で、電子取引データを紙に印刷して整理されている場合は、第3の問いの回答は「Yes」です。そうでない場合は、「No」に進んでください。(「No」にジャンプ)
【Q3】の回答が「Yes」の場合
【Q3】の回答が「Yes」であった場合は、
これができていれば、電子取引データに関しては、電子帳簿保存法で認められた電子保存が行われていることになります。ここで判断は完了です
【Q3】の回答が「No」の場合
【Q3】の回答が「No」であった場合は、【Q4】に進んでください。
【Q4】税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じることができるようにしているか?

第4の問いは、
【Q4】の回答が「Yes」の場合
【Q4】の回答が「Yes」の場合は、次の3つの条件を設定して、電子保存している電子取引データを検索できるようにしていればOKです。
❶ 取引年月日その他の日付
❷ 取引金額
❸ 取引先
これができていれば、電子取引データに関しては、電子帳簿保存法で認められた電子保存が行われていることになります。ここで判断は完了です
これができないと電子帳簿保存法で認められる電子保存をしていないことになるんですか?
結構たいへんじゃないですか?この要件。
システムを導入しなくても、表計算ソフト等を使った検索要件を満たす方法を国税庁が紹介していますよ。
国税庁が紹介している検索要件を満たすための簡易な方法とは
① 表計算ソフト等で索引簿を作成して、表計算ソフト等の検索機能を使って検索する方法。

(国税庁のパンフレットから抜粋)
② データのファイル名を規則性を持たせて「日付_金額_取引先」のように入力し、特定のフォルダに保存しておくことで、フォルダの検索機能を使って検索する方法。

(国税庁のパンフレットから抜粋)
うーん、本業が忙しくて、このような検索システムを用意できそうもないなぁ
これができないとダメなんですか?
いいえ。
実は、この令和5年改正の電子帳簿保存法では、このような検索システムを用意できない場合は、次の要件に当てはまれば、すべての保存要件が免除されるという猶予措置があります。
ただし、紙に印刷して保存することは認められませんので、その点は誤らないように!
取引年月日・金額・取引先で検索できるような方法を準備することができない場合は猶予措置を適用
取引年月日等、取引金額、取引先の3つの項目で検索できるシステムを用意できない場合は、猶予措置を適用することで、電子取引データに関しては、電子帳簿保存法で認められた電子保存が行われていることになります。
猶予措置を適用するを確認して、その適用を受ける施策を講じれば電子取引データの電子帳簿保存はOKです
【Q4】の回答が「No」の場合
【Q4】の回答が「No」の場合は、
- 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定することができること。
- 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
- 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
この検索要件を満たすシステムなんかを用意できなかったらどうなりますか?
このような検索システムを用意できない場合は、次の要件に当てはまれば、すべての保存要件が免除されるという猶予措置があります。
3つの方法で検索できるようなシステムを準備することができない場合は猶予措置を適用
猶予措置を適用することで、電子取引データに関しては、電子帳簿保存法で認められた電子保存が行われていることになります。
猶予措置を適用するを確認して、その適用を受ける施策を講じれば電子取引データの電子帳簿保存はOKです
まとめ

電子取引データに関する電子帳簿保存法は、当初厳しい保存要件を事業者全員に適用しようとしたところ、2022年1月の施行開始直前に苦情が殺到したために、紙でもOKという宥恕規定ができた経緯があります。
その反省を踏まえて、本来は次の保存要件を具備して電子取引データを電子保存しなければならないのですが、猶予措置を設けてどんな事業者でも電子保存を実施できるようにしたというのが、現在の電子取引データに関する電子帳簿保存です。
電子取引データの原則の電子保存3要件
- コンピュータ、ディスプレイとプリンタの備え付け
- 不正な改ざん防止策を講じる
- 検索機能の確保
したがって、電子取引データの電子保存が何をしていいかわからないという方は、以下の猶予措置を適用すれば、上記の電子保存3要件はすべて免除され、電子取引データを何らかの形で電子保存していれば、なんら問題がありません。
電子取引データの電子保存に関する猶予措置
システム等の整備が間に合わない場合など、上記の電子保存3要件に従って電子取引データの保存を行うための環境が整っていない事情がある場合
- その電子データ
- その電子データが書面で作成された場合に準じた形式で出力した書面
電子保存3要件のうちのコンピュータ、ディスプレイとプリンタの備え付けについては、税務職員へ提示または提出が必要になる関係上必要になります。
なお、プリンタに関しては、近隣に有料コピー機があって、速やかに印刷できれば問題ないことになっています。
一つ注意点があるとすれば、あくまで電子取引データは電子的に保存しなければならず、電子取引データを印刷して紙の状態で保存することは、2024年1月以降できなくなります。これをやると、最悪の場合、青色申告取り消しということを税務署にされても文句は言えません。
なお、電子保存しないことによる青色申告取り消しについては、電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問65(国税庁)において、次のように厳しくは適用していかない旨の解説があります。
青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用を判断して います。 – 略 – その申告内容の適正性については、税務調査において、納税者からの追加的な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。
このように猶予措置は、広く適用されるものと考えられていますので、2024年1月からの義務化される電子取引データの電子帳簿保存法は、恐れる必要はないことをご理解いただけたと思います。
電子帳簿保存法のルールの中でどのように電子取引データを電子保存すべきかをQ&A方式で確認してきましたが、もう一度ここで確認しておきましょう。

国税庁でも少しこちらの記事の説明の仕方とは異なる部分もありますが(内容は同じ)、電子取引データの電子保存の対応を図解しているペライチがありますので、そちらも紹介しておきます。
まとめたいと思います。
2024年1月からの義務化される電子取引データの電子帳簿保存法について、電子保存3要件に対応できない事業者は、
また、2022年1月当時の改正電子帳簿保存法の施行時にすでに電子保存3要件にしたがったシステムを導入している事業者は、原則どおり電子保存する必要があります。
これを機に、電子保存3要件を具備して電子帳簿保存法の原則のルールを適用したいという事業者は、何らかのシステムを導入するというのが、効率的に対応する方法かと思います。
その場合は、かんたんに電子保存3要件に対応できて、100円から始められる当社の全力電子帳簿のご利用をご検討ください。
無料で10ファイルの保存が可能です。




 元国税税理士
元国税税理士
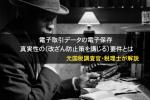






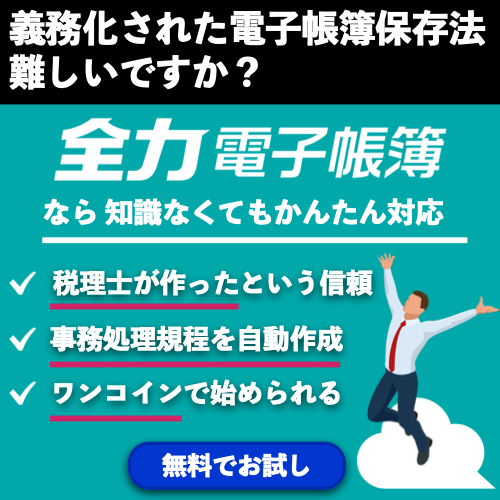
コメント