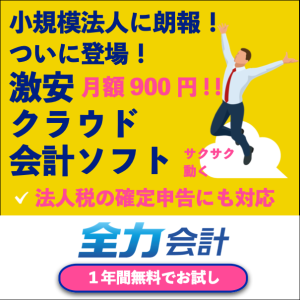勘定科目の「雑収入」について、具体例をふんだんに使って簿記初心者にもわかりやすく解説します。
1「雑収入」が使われる取引例
勘定科目の「雑収入」で経理される主な取引例は以下のとおりです。
| 内容 | 具体例 |
|---|---|
| その他 |
|
2「雑収入」とは
2-1 勘定科目「雑収入」とは
「雑収入」で経理されるものは、本業から得ている収入ではないが、経常的に発生する収入で、他の営業外収益に分類されるの勘定科目にあてはまらないもの、または独立の勘定科目を用いるほど重要でない少額の収益です。
一般的な営業外収益の勘定科目は次のようなものがあります。
受取利息、受取配当金、有価証券利息、仕入割引、有価証券売却益、有価証券評価益、投資有価証券売却益、為替差益
特別利益とも混同しやすいのでその点も注意しましょう。特別利益との違いは後述します。
別の言い方をすると、売上高にも特別利益にも当てはまらない営業外収益のうち、他の勘定科目にあてはまらないものとも言えます。(後述)
2-2 勘定科目「雑収入」の特徴
「雑収入」の会計上おさえておくべき特徴は次のとおりです。
| グループ | 「収益」グループ |
|---|---|
| 決算書の表示 | 営業外収益 |
| 類似科目 | なし |
| 税区分 | 課税売上or対象外 |
| インボイス有無の判定 | 不要 |
3「雑収入」の仕訳例
歯医者で金属クズを売却して、その代金220,000円(税込10 %)を振込で受け取ったケース費用を現金で支払ったケース
【税込経理方式】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 220,000 | 雑収入 | 220,000 |
【税抜経理方式】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 220,000 | 雑収入 | 220,000 |
| 仮受消費税等 | 20,000 |
4「雑収入」処理上のその他の注意点
4-1 雑収入はどのような時に計上するのか
雑収入は、本業とは直接関係のない活動で経常的に得ている収益(営業外収益)のうち、他の勘定科目にあてはまらないものを処理するための会計項目と説明しました。
具体的には、製造業などで鉄板を加工するときに出る鉄屑を売却する場合は、製品の売上が本業の売上になります。その製造過程で出る副産物を売却して得た収入は、本業の売上ではありませんが、経常的に発生するため雑収入に計上します。
また独立の勘定科目を用いるほど重要でない少額の収益に対しても雑収入を用います。
少額とはどのくらいかというと、売上高の5%くらいまでを目安にしておくとよいでしょう。
例えば国からの補助金や助成金収入は本業とは直接関係ありませんが、多額とまでは言えないものは「雑収入」に計上されるのが一般的です。
売上が1億ある会社が100万円の助成金を得た場合は、少額として「雑収入」としてよいでしょう。また、売上高が1千万円の会社が100万円の助成金を得た場合は、特別利益とするのがよいでしょう。
売上高の10%以上の雑収入が計上されていたら、税務署や金融機関の者が見たら「?」と思うのは必至です。そのような場合は中身が何かわかるように別の勘定科目を設定すべきでしょう。
他の科目に当てはまらない場合は、新しい科目を設定してどのような収入なのかを明示するようにしましょう。
4-2 特別利益と営業外収益との違い
「営業外収益」と似た収入に「特別利益」もあります。特別利益に当てはまるものは、雑収入には計上しませんので注意しましょう。
4-2-1 特別利益とは
特別利益とは、本業とは関わりのない収入で、(ここまでは営業外収益と同じです。)当期にだけ発生するような臨時的な収入で金額的に多額な取引を経理する項目です。
一般的な特別利益の勘定科目は次のようなものがあります。
固定資産売却益、投資有価証券売却益、貸倒引当金戻入額、受取保険金、受贈益、債務免除益、国庫補助金収入、前期損益修正益、償却済債権取立益
固定資産を売却するということは、そうしょっちゅうあるものではありません。また、金額も多額になりがちです。保険金の受け取り、助成金や補助金収入も特別利益に分類されます。
4-2-1 特別利益と営業外収益との違い
特別利益と営業外収益の違いは大きく以下の2つです。
| 特別利益 | 営業外収益 | |
|---|---|---|
| 発生頻度 | 当期のみのように臨時的 | 経常的に発生する傾向 (まれに発生も可) |
| 金額の大小 | 多額な収入 | 少額の収入 |
本業に関係がなく、臨時的で多額な収入が特別利益です。特別利益でも売上高でもない収入が、営業外収益に分類されます。
つまり、本業に関係ない収入で経常的に発生する場合は、「営業外収益」になります。
また、本業に関係ない収入で少額なものも「営業外収益」になります。
基本的には当期だけ発生するようなまれで多額な取引は、特別利益に分類され、それ以外で本業とは関わりのない収入は、営業外収益だと考えてOKです。
補助金や助成金は、金額が大きく臨時的なものは特別利益で処理し、それ以外のものは雑収入で処理します。
いくら以上が多額かは特に定められておりませんし、会社の規模によっても変わってきますので、会社でラインを決めて継続適用していれば問題ありません。雑収入と特別利益の分類を間違えたとしても罰則があるわけではありませんので、あまりここは神経質になる部分ではありません。
4-3 消費税の課否判定
例えば、給与は消費税がかからない、法定福利費は消費税がかからないといったように、雑収入は消費税がかかる取引とは言い切れません。
取引内容によって消費税がかかる、かからないが決まってきます。
消費税がかかるorかからないの判定(課否判定)は実はかなり難しい判定となります。
詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。わかりやすく詳しく解説しています。
ここでは代表的な消費税の課否判定を挙げておきます。
| 取引内容 | 消費税の課否判定 |
|---|---|
| 税金の還付金 | かからない(不課税) |
| 税抜経理方式の場合の消費税の精算差額 | かからない(不課税) |
| 助成金収入や補助金収入 | かからない(不課税) |
| 協賛金収入 | 宣伝効果あり→かかる(課税) 明確な対価性なし→かからない(不課税) |
| 社宅の家賃収入 | かからない(非課税) |
| 駐車場の賃貸収入 | かかる(課税) |
| 鉄クズ等の副産物を国内の業者へ売却 | かかる(課税) |
| 国内の代理店の手数料収入 | かかる(課税) |
| 自動販売機の手数料収入 | かかる(課税) |
| 御祝儀の受け取り | かからない(不課税) |
勘定科目「雑収入」に関する解説は以上です。
この取引がどの勘定科目に当てはまるかわからない、教えてほしいということがあったらコメントくださいね。
法人の決算と確定申告を自分でしたい人のために生まれたクラウド会計ソフト「全力会計」

初心者向け 小規模法人用 クラウド会計ソフト「全力会計」
利用社数 28,000 超え 顧客満足度 93.4 %の クラウドソフトで初めて法人税の自力申告を成功させた全力法人税からついに会計ソフトが登場!
・とにかく安い(月額900円+税)
・動作がサクサク高速
・法人税の確定申告まで一気通貫
・簿記初心者に優しい機能満載
・1年間無料で試せる
マイクロ法人や小規模法人は求めていた!
そんなにたくさん便利機能はいらないから小規模な法人に必要十分の機能だけ搭載されていてもっとシンプルで安い会計ソフトがほしいんだ!
でもそんな会計ソフトこれまでなかった。
そしてついに登場したのだ!!
税理士に頼らず決算から確定申告まで自分の手でこなせる優れもの!
こんな会計ソフトを待っていた!
⇩